宮下和男先生のページ

宮下和男先生は、信州児童文学会の草創期より、会の発展に尽力されてこられた日本児童文学界の重鎮とも呼べる作家です。
2017年5月25日に多くの人々に惜しまれつつ他界されましたが、児童文学のあるべき姿を追い続けるとともに、子どもたちと真正面から向きあう教育姿勢をつらぬいてこられた先生の作品には、子どもたちへの愛情と現実社会での厳しさをあわせ持った奥深さが満ちています。
長年の教師生活をされてきた先生の描く子どもたちには、設定におけるあいまいさがひとつもなく、また、彼らの生きる背景からも、その時代を感じさせるような空気が、味やにおいまで伴いながら読者に伝わってきます。
数多くの著作を残されていますが、ここでは、現在入手可能な出版物を中心にご紹介させていただきます。
プロフィール

宮下和男
1930年、長野県飯田市うまれ。
元信州児童文学会会長。現在、顧問。
日本児童文学者協会会員。
元飯田女子短期大学教授。
1968年「きょうまんさまの夜」(福音館書店)で第1回日本児童文学者協会新人賞。
主な著書に「ばんどりだいこ」(ポプラ社)、「しかうちまつり」(大日本出版)、「春の迷路」(ほるぷ出版)、「少年の城」(岩崎書店)、「落ちてきた星たち」(岩崎書店)、「少年・椋鳩十物語」(理論社)、「野生のうた・椋鳩十の生涯」(一草舎)等、多数。
とうげの旗
「とうげの旗」は、1971年に信州児童文学会から創刊され、日本で最も長期にわたって発行され続けた児童文学雑誌です。
2012年2月発行の第162号をもって終刊となりましたが、「親子で読みあう雑誌」と銘打ち、多くの少年少女たちに夢と希望を与え続けてきました。
現在は、信州児童文学会の会誌として、児童文学作家たちの作品発表の場となっています。

「別冊とうげの旗 宮下和男追悼」
信州児童文学会より、平成29年5月25日に多くの人に惜しまれつつご逝去された宮下和男先生の追悼集が発行されました。
信州児童文学会の会長として長きに渡って会の発展と後輩の育成に尽力されたその功績は、信州のみならず日本の児童文学界においても、今なお燦然とした輝きを放っています。
また、多くの著書を残し「児童文学かくあるべき」との模範を若い作家たちに示し続けてこられました。
これは、偉大な先師であられた宮下先生をしのび、現会長の北沢彰利先生を中心に編集された追悼集です。
また、宮下先生の生い立ちから教師歴、家族歴、文学歴、さらにはその文学性等にも触れられており、宮下文学を知る上での貴重な資料ともなっています。
頒価1,500円
発行 信州児童文学会

「里山少年記 続・分教場ものがたり」
「分教場ものがたり」の主人公である和彦のその後を描いた短編。
五年生となった和彦が、本校のサカダニ国民学校へと通いだしたところから物語ははじまる。
担任の長谷川先生から音楽や習字など、様々な学問を教わる和彦。
そんな和彦も、同級生の「かぐや姫」南沢珠代のことが気になるなど、少しずつ大人になっていく。
高等科に進んだ和彦は、岩山先生の勧めに従って、学校の先生になろうと決意する。
しかし、その間にも太平洋戦争はますます激しくなり、和彦たちの生活にも暗い影を落とすようになる・・・。
前作「分教場ものがたり」で生き生きと描かれていた和彦が、宮下先生ご本人の投影であることに気づかされる後日談です。
短編ですが、前作に引き続き里山での素朴な生活観にあふれ、読む者を楽しませてくれます。
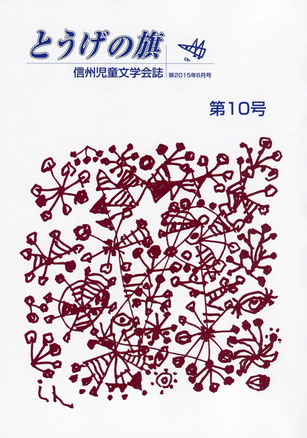
「評論 椋文学の源流をさぐる」
長野県出身の児童文学者「椋鳩十」(本名久保田彦穂)について、詳しく解説された評論。
椋は、野生動物を主人公にした小説を多く書いているので、「動物児童文学者」というレッテルをはられているが、本人は、それを強く拒んでいた。
彼は、渡邊修三や竹中又七、潮田武雄とともに詩誌「リアン」を創刊しているが、そこに「のんせんす(ナンセンス)の芸術」という評論を残している。
椋は、シュール・リアリズム(超現実主義)の賛同者であり、後に彼の作風を形作る山窩小説も、そこからスタートしているのではないかとの指摘は、椋文学の新しい考察として興味深い。
また、椋の書いた児童小説や大衆小説の紹介もされており、椋文学を知る上での入門書としても貴重な評論となっている。

「分教場ものがたり」
小学校の教員をしている夫婦と、二人の子どもたちの日常を描いた物語。
昭和13年、教員の源吾が妻のきぬと六人の子どもをつれて長野県の山中にあるヤマネ分教場にやってきた。
苛酷な環境ではあるが、素朴な幸福感に満たされた生活に、しだいになれていく子どもたち。
飼っていたスズメの話や夏の野営(キャンプ)でのできごとなど、美しい自然の中でのびのびと成長していく子どもたちの様子が、まぶしく感じられる。
カッパのような姿をした「かわらんべのツネ」が登場したあたりから、物語は、さらにおもしろさを増し、グイグイと読者を引きこんでいく。
しかし、そんな楽しいヤマネ地区の生活にも、しだいに戦争の暗い影が忍び寄ってくる。
心を病んだ「お里」と和彦のふれあいが切なく描かれ、物語は終盤を迎える。
全体を通して、文章のひとつひとつが、強烈に心に響き、まるで映像を見せられているかのような錯覚を覚えるほどの力強さがある。
これは、宮下先生が子どものころに体験した、心の原風景なのかもしれない。
志賀直哉は、よい文章を「風景が見えるようだ」と評したというが、本作品は、まさに「風景が見える」どころか、当時の空気までも感じさせる、宮下文学の集大成である。



